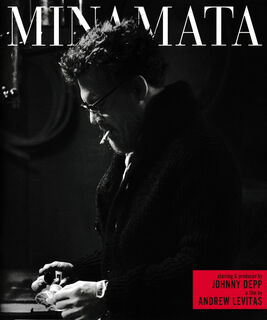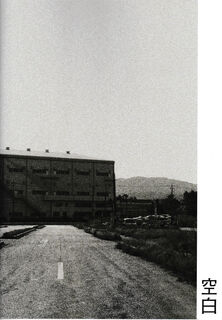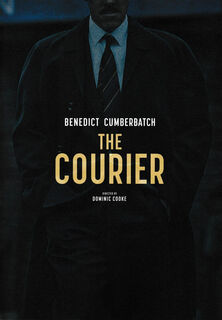ドキュメンタリー番組のディレクター由宇子(瀧内公美)が女子高生いじめ自殺事件の真相を追う番組の制作で報道被害やネットの誹謗中傷のひどさを描くのが発端。女子高生は講師と関係を持っていたと疑われ、その講師の方も自殺。遺書には抗議の意味をこめて、と書かれていた。由宇子は仕事の傍ら、父親(光石研)の学習塾を手伝っているが、その父親の衝撃的な事実を知らされる。父親のことが世間に知られれば、自分の仕事にも影響する。由宇子は究極の選択を迫られる、というストーリー。
由宇子は取材を進める事件と父親の問題の2つを抱えるわけですが、どちらもほぼ先行きが分かったと思わせた段階でさらに新しい事実が判明します。この映画、いじめや報道被害や貧困を描いていますが、だから傑作なのではなく、この物語の作りが優れているからだと思います。物語のヒントになったのは2014年のいじめ自殺事件の際、無関係の同姓同名男性がネットリンチに遭った事件とのこと。これが一見、単純な事件の奥にある複雑な物語の作りになったのではないかと思います。
同時に春本雄二郎監督の描写のうまさが光っており、由宇子が体調を崩した貧困家庭の女子高生に雑炊を作って食べさせる場面や、世間から隠れてひっそりと暮らす講師の母親(丘みつ子)と講師が好きだったパンを一緒に食べる場面など温かみのある描写になっていて実にうまいです。瀧内公美もまたまた有力な主演女優賞候補でしょう。
フランク・ハーバートの名作SFをドゥニ・ヴィルヌーヴ監督が映画化。西暦10190年、レト・アトレイデス公爵(オスカー・アイザック)は皇帝の命を受けて、砂の惑星アラキス(デューン)を治めることになる。そこは抗老化作用のほか、宇宙を支配する能力を与えるスパイス“メランジ”の唯一の生産地で、アトレイデス家には莫大な利益がもたらされるはずだった。しかし妻のジェシカ(レベッカ・ファーガソン)と息子のポール(ティモシー・シャラメ)を連れてデューンに乗り込んだレト公爵を待っていたのはメランジの採掘権を持つ宿敵ハルコンネン家と皇帝が結託した陰謀。壮絶な戦いで父を殺され、地位を追われたポールは現地の自由民フレメンの中に紛れることになる。
1984年のデヴィッド・リンチ監督版を僕は見ていなかったので、先日見ました。漫画チックと言える作りに加えてダイジェスト感は否めず、今回のヴィルヌーヴ版の足下にもおよびません。ヴィルヌーヴが取ったのは正攻法、高尚、高級、高規格の画面作りにほかならず、始まって30分ぐらいは「すげえ、これはすげえ」と画面に見惚れていました。
ただし、メインタイトルと一緒にパート1と示されるだけあって、2時間35分かけてもなかなかストーリーが進みません。加えて主人公側がメタメタにやられる展開で、「スター・ウォーズ」で言えば、「帝国の逆襲」のようなもの。「帝国の逆襲」は傑作でしたが、この映画の場合、キャラクターに深く感情移入するには至らず、巨大な砂虫(サンドワーム)の見せ場も少なく、「帝国の逆襲」ほどのドラマ性は備えていません。評論家の評価は高いにもかかわらず、一般観客の支持があまり高まらないのはそうしたことが影響しているのかもしれません。
いずれにしてもヴィルヌーヴには一刻も早く主人公たちが反転攻勢するパート2を作ってほしいところです。
今年のアカデミー賞で国際長編映画賞を受賞したデンマークのトマス・ヴィンターベア監督作品。主演はいつもコンビを組んでいるマッツ・ミケルセン。
冴えない4人の中年高校教師が「血中アルコール濃度を0.05%に保つと、仕事の効率が良くなり、想像力がみなぎる」という理論を確かめるため実際に酒を飲んで授業を行う。ほろ酔い状態だと、授業も楽しくなり、生徒たちとの関係も良くなっていく。仕事だけでなくプライベートも好転するかと思われたが、実験が進むにつれて制御が利かなくなってしまう。
アルコール濃度を保つと好転する→保たないとダメになる、という風に依存が強まっていく展開は目に見えていて、基本コメディなんですが、事態は笑えない展開になっていきます。仕事のほか、それぞれに家庭にも問題を抱えた中年男のクライシスを描いているのが共感を呼ぶ部分かもしれません。でも、問題を酒で解決しようとするのはやはり無理があるのでしょう。
字幕で出るアルコール濃度の単位は‰(パーミル)でしたが、デンマークでは普通にこれを使うんでしょうかね。デンマークでは16歳から酒が買えるそうで、劇中、面接の緊張緩和のため先生が生徒に酒を勧める場面があっても、違法ではないわけですね。
東京在住の2人のクルド人青年に焦点を当てたドキュメンタリー。
オザンとラマザンはトルコ国籍のクルド人で、身の危険を感じて家族と小学生の頃に日本に逃げてきた。
家族ともども難民申請をしているが、認められず、不法滞在状態で入管への収容をいったん解除される仮放免の身分。不法滞在なので働くことは禁じられ、もちろん健康保険等もない。2カ月に一度、入管に行き、現状報告する義務がある。
日本政府がクルド人を難民と認定したことはないそうで、こうした宙ぶらりんな状態が何年も続くことになっています。
クルド人に限らず、日本政府が難民認定に消極的、というか、追い返す施策を取っているのは難民が増えるのを警戒しているからでしょう。
世界5位の移民大国になったにもかかわらず、通常の移民よりも困っている人たちに手を差し伸べないことには疑問を感じます。
日本政府に必要なのは人道的観点からの施策でしょう。
監督はテレビドキュメンタリーを手がけてきた日向史有。
フランス人のアルチュール・アラリが監督。
1974年までの戦後29年間、終戦を知らずにフィリピンのルバング島で戦った小野田寛郎元少尉を描いています。
小野田元少尉と言えば、僕は軍刀をフィリピン軍の司令官に渡す場面をテレビで見たのを覚えています。
投降する際の旧日本軍の作法だったと説明され、会見で述べた言葉も含めて「恥ずかしながら帰って参りました」の横井庄一さん(元軍曹)とは違うな、さすが将校だと思えましたし、一般的な評価もそうでした。
映画には小野田がルバング島の住民を殺す場面が3度描かれ、こういうこともあったんだと驚きますが、実際には3人どころではなく、本人の言葉によると、30人を殺害、100人に負傷させたそうです。
そうした小野田の負の側面は当時から一部報道されていたようですが、賞賛の世論の中に埋もれていました。
ルバング島民にとって、小野田とは29年間にわたって略奪と殺傷を繰り返してきた凶悪な犯罪者にほかならないでしょう。
小野田が終戦を知らなかったということを疑問視する見方もあります(ラジオで日本の短波放送を聞いていたのですから知らなかったはずはないでしょう)。
アラリ監督は父親から聞いて小野田のことを知り、、日本在住のジャーナリストだったベルナール・サンドロンの著書「ONODA」を読んで映画化を決めたそうです。
174分という長尺なのでジャングルシーンなど長すぎると思えますが、負の側面を最小限に抑えたフィクションとして見るならよく出来ています。
壮年期の小野田を演じる津田寛治はかなり体重を落として外見を似せていますし、小野田を発見して日本に帰国させる役割を果たす冒険家・鈴木紀夫を演じる仲野太賀、小野田のかつての上官谷口役のイッセー尾形らも好演しています。
全編日本語であることを考えると、アラリ監督の演出は的確です。
ちなみに「野生のパンダと小野田さんと雪男に会うのが夢」と話していた鈴木紀夫は2つを実現した後、3つ目を目指してヒマラヤに行き、遭難死したそうです。
シリーズ25作目で上映時間はシリーズ最長の2時間44分。
「ダニエル・クレイグ版ジェームズ・ボンドは最後」とアナウンスされているにしても長すぎるのでは、と見る前は思ってました。
でもこの内容なら仕方ないかなと思います。
KINENOTEから粗筋を引用すると、「現役を退いたボンドは、ジャマイカで穏やかな生活を満喫していた。しかし、CIA出身の旧友フィリックス・ライターが助けを求めてきたことで平穏な生活は突如終わってしまう。誘拐された科学者を救出するという任務は、想像以上に危険なものだった……」。
この紹介は何も言っていないに等しいですが、この映画、激しくネタバレ禁止の内容でした。
この内容ならば、もっと情感たっぷりに描いて欲しいところなのに、キャリー・ジョージ・フクナガ監督の演出はドラマティックな盛り上げ方がうまくありません。
敵役のラミ・マレックもダニエル・クレイグの相手としては役不足の感じがあります。
しかし「女王陛下の007」のようにエモーショナルな展開ではあり、シリーズのファンであるなら、必見の作品であることは間違いありません。
1年前にリリースされたビリー・アイリッシュのややブルーな主題歌もオープニング映像に合わせて聞くと、さらに良かったです。
キューバでボンドを支援するCIAの女エージェントが格好良くて美人だなと思ったら、アナ・デ・アルマス(「ブレードランナー 2049」「ノック・ノック」)じゃありませんか。
エンドクレジットの最後にはいつものように「James Bond Will Return」と出ます。
「明日の食卓」に続いて今年2本目の瀬々敬久監督作品。
東日本大震災と生活保護を絡めたテーマは重いですが、これに連続殺人まで絡めなくても良かったのではないでしょうかね。
ミステリーとしては犯人の動機の設定が弱いです。
2人を縛ったまま放置して餓死させ、さらに3人目まで狙うというのは相当な恨みの感情が必要ですが、それを納得させる描写が足りませんでした。
殺人の動機となった出来事から何年もたってなぜ犯行に及んだのかの説明もありません(これは中山七里の原作も同じだそうです)。
加えて制度・運用上の欠陥を現場の個人の責任に帰す犯人の考え方は近視眼的すぎるほか、狙われる1人の代議士はそうした欠陥を知った上で現状改善を含めた福祉向上を訴えており、いわば同士討ちの様相になっています。
佐藤健、清原果耶、阿部寛、倍賞美津子らの演技に深く感心しながらも、この脚本ではダメだという思いが沸々とわいてきました。
瀬々敬久監督は「明日の食卓」もそうでしたが、物語の不備に気づいていないか、気づいても修正能力がないのでしょう。
演出の技術は高いので、誰か優秀な脚本家と組んだ方が良いと思います。
いわゆる扶養照会が生活保護の受給をためらわせる原因となるケースは多いと聞きます。
子どもや親族に自分の窮状を知られたくない、迷惑をかけたくないという気持ちはよく分かりますが、その結果、保護費を受給せずに苦しんだり、病気になったりするのはおかしいでしょう。
人命を第一に考えて、制度運用を改め、早急に保護を決定してほしいものです。
震災の避難所で老婆と若者、子どもが出会い、疑似家族を形成するという出だしは「岬のマヨイガ」と同じでした。若者の男女の違いはありますけど。
「ベイビーわるきゅーれ」の殺し屋女子2人組(高石あかり、伊澤彩織)のアイデアの元になった阪元裕吾監督「ある用務員」をU-NEXT(お試し会員登録中)で見た。
元暴力団員だった父を持つ深見晃(福士誠治)は高校の用務員として働きながら、父の兄弟分である真島(山路和弘)の娘・唯(芋生悠)のボディーガードとして密かな人生を送っていた。ある日、暴力団の抗争が勃発し、唯が標的にされてしまう。学校を襲撃してきた9人の殺し屋たちに深見は単身立ち向かう、というストーリー。
高石あかりと伊澤彩織は中盤に登場、派手なアクションを繰り広げる。アクション監督はクレジットされていないが、伊澤彩織の福士誠治との格闘シーンは「ベイビーわるきゅーれ」同様にスピード感があり、見応え十分。公開時に行われた舞台あいさつで伊澤彩織は「(福士誠治に首を絞められて絶命するシーンは)あと3秒続いていたら落ちていた」と話していた。どうりで顔が赤黒く、真に迫っていたわけだ。
この映画、1月に「未体験ゾーンの映画たち」の1本として東京で公開されたが、九州では福岡のみの公開。10月25日のDVDリリースに先立ってU-NEXTで配信したのはU-NEXTが製作委員会に入っているからだろう。
U-NEXTには以前から興味があったが、月額2189円(税込み)は他の配信サービスに比べて高く感じる。U-NEXT月額プランの料金詳細によると、「ビデオ見放題:1,089円 雑誌読み放題:550円 1,200ポイント:550円」という考え方だそうだ。毎月付与される1200ポイントは劇場公開から間もない新作などの観賞に必要で、399ポイントの作品が多いようなので3本は見られる計算。それが550円なのはお得と考えても良いが、強制的に550円使わせる仕組みとも言える。
さらに不要なのは雑誌読み放題だ。「月額プラン1490」(税込み1639円)はこれを外して「1200ポイント」を入れてほしい。あるいは基本サービスを見放題の1089円だけにして、あとのサービスはトッピングで加えられる仕組みにした方がリーズナブルだし、理解を得やすいと思う。そうなると、雑誌読み放題が550円では楽天マガジンやdマガジンには対抗できないですけどね。