2006/01/18(水)「亀も空を飛ぶ」
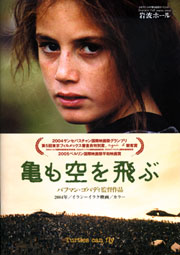 キネ旬ベストテン3位。イランに住むクルド人監督であるバフマン・ゴバディがイラク北部の村に生きるクルド人の子供たちの過酷な生活を描く。地雷で手や足をなくした子供が普通にいたり、除去した地雷を売って生活の糧を得る子供たちの姿、過去の恐ろしい出来事に心を痛め、いつも無表情な少女の姿には言葉を失うが、この映画が優れているのは両腕をなくした少年が予知能力を持っているというファンタスティックな設定や日々のユーモアを織り込んで普遍的な映画に仕上げていることだ。現実から近いところで成立させたフィクションで、現実に軸足を置きつつ、フィクションの有効性を最大限に生かしている。クルド人の監督だから、描いてあるのは弾圧と迫害と虐殺にさらされてきたクルド人の悲惨な現状なのだが、これは単に戦争の犠牲になるのはいつも子供たちだ、という風に設定を無視して短絡的に受け取ってしまっても悪くはないと思う。映画を見た後、すぐにどこかの子供を救える募金に協力したくなる気分にさせる映画である。
キネ旬ベストテン3位。イランに住むクルド人監督であるバフマン・ゴバディがイラク北部の村に生きるクルド人の子供たちの過酷な生活を描く。地雷で手や足をなくした子供が普通にいたり、除去した地雷を売って生活の糧を得る子供たちの姿、過去の恐ろしい出来事に心を痛め、いつも無表情な少女の姿には言葉を失うが、この映画が優れているのは両腕をなくした少年が予知能力を持っているというファンタスティックな設定や日々のユーモアを織り込んで普遍的な映画に仕上げていることだ。現実から近いところで成立させたフィクションで、現実に軸足を置きつつ、フィクションの有効性を最大限に生かしている。クルド人の監督だから、描いてあるのは弾圧と迫害と虐殺にさらされてきたクルド人の悲惨な現状なのだが、これは単に戦争の犠牲になるのはいつも子供たちだ、という風に設定を無視して短絡的に受け取ってしまっても悪くはないと思う。映画を見た後、すぐにどこかの子供を救える募金に協力したくなる気分にさせる映画である。
アメリカのイラク侵攻前の2003年春、トルコ国境に隣接する北部の村が舞台。大人たちは間もなく始まる戦争の情報を得ようと、テレビのアンテナを立てるのに必死だ。主人公の少年ソランはそうした衛星アンテナの設置も行っているのでサテライトと呼ばれる。サテライトは村の子供たちを率いて、地雷を除去し、それを売っている。ある日、この村に両腕をなくした少年ヘンゴウと赤ん坊リガーを背負った少女アグリンの兄妹がやってくる。アグリンに一目惚れしたサテライトは何かと世話をするようになる。ヘンゴウは地雷の埋まった場所を言い当てたり、トラックの爆発を予言したりする。予知能力があるらしい。アグリンはいつも無表情で、なぜかリガーを嫌っている。
こうした設定の下、映画は村の子供たちの日常を活写していく。子供たちはただ悲惨ではなく、笑顔も見せるし、たくましさもあるが、そうした姿が逆に痛ましい気分を起こさせる。しかし、個人的に心を揺さぶられたのは過酷な子供たちの姿よりも、地雷原の中に迷い込んだ幼児を助けようとする主人公サテライトの姿。子供たちのリーダーで、要領のいいだけの少年かと思えたサテライト、実はしっかりしたいいやつなのである。サテライトは戦争孤児で、アメリカに憧れている。フセインから弾圧を受けてきたクルド人にとって、アメリカの侵攻は弾圧からの解放を意味する。政治的な観点から見れば、アメリカはベトナム戦争でも北ベトナム政府から迫害されていた山岳民族に反政府勢力を組織させたし、この映画もそういう風に利用される恐れがあったが、ゴバディはアメリカを信用していず、「独裁者がフセインから変わっただけ」というスタンスのようだ。化学兵器で虐殺を行ったフセインよりはまし、といったところか。アカデミー外国語映画賞のイランの代表作品になったにもかかわらず、賞にノミネートされなかったのはそういう部分があるからかもしれない。
イラクではアメリカの後押しによってクルド人の大統領が誕生したが、クルド人が本当に弾圧と迫害から逃れるためにはクルド人の国を作るしかないだろう。クルド人はトルコ、イラン、イラク、シリアなどに分散しているから問題は複雑で、そのめどは全くない。民族と住む国が一致しない悲劇(母国語と母語が一致しない悲劇)はいつになったら解消されるのだろう。
パンフレットによれば、映画でヘンゴウを演じる少年ヒラシュ・ファシル・ラーマンは実際には地雷ではなく、感電事故で両腕をなくしたそうだ。本当に目が見えなかったリガー役の赤ん坊アブドラーマン・キャリムはその後手術を受け、視力を取り戻したという。
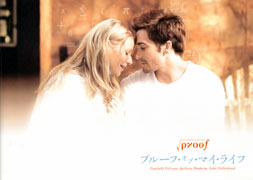 数々の賞に輝くデヴィッド・オーバーンの戯曲「プルーフ/証明」をジョン・マッデン監督とグウィネス・パルトロウの「恋におちたシェイクスピア」コンビで映画化。マッデンとパルトロウは2002年のロンドンの舞台でも演出・主演を務め、高い評価を受けたという。手慣れた題材のはずだが、なかなか話が見えてこない映画の前半が思わしくない出来なのは映画化にあたって付け加えたという葬儀とパーティーのシーンがやや精彩を欠くためか。舞台劇らしく会話が多いことも映画的なノリにブレーキをかけているようだ。
数々の賞に輝くデヴィッド・オーバーンの戯曲「プルーフ/証明」をジョン・マッデン監督とグウィネス・パルトロウの「恋におちたシェイクスピア」コンビで映画化。マッデンとパルトロウは2002年のロンドンの舞台でも演出・主演を務め、高い評価を受けたという。手慣れた題材のはずだが、なかなか話が見えてこない映画の前半が思わしくない出来なのは映画化にあたって付け加えたという葬儀とパーティーのシーンがやや精彩を欠くためか。舞台劇らしく会話が多いことも映画的なノリにブレーキをかけているようだ。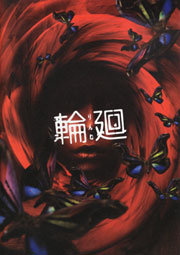 「呪怨」の清水崇監督の新作で、35年前に大量殺人があったホテルを題材にした映画のスタッフとキャストが怪異に襲われるホラー。中心となるアイデアは過去にも例があり、ちょっと考えただけで、設定は異なるけれどもポール・バーホーベンのあの作品とかアラン・パーカーのあの作品が思い浮かぶ。リーインカーネーションを描いた映画としてはこうするか、それこそ「リーインカーネーション」(1976年、J・リー・トンプソン監督)のようにするかしかないのだろう。また、大量殺人のあったホテルと言えば、スティーブン・キング「シャイニング」=映画化はスタンリー・キューブリック=を思い出さずにはいられず、「輪廻」は幽霊屋敷もののバリエーションとも言える(幽霊屋敷の最高傑作は「シャイニング」ではなくリチャード・マシスン「地獄の家」=映画化はジョン・ハフ「ヘル・ハウス」=だと思う)。考えてみれば、「呪怨」自体、幽霊屋敷もののバリエーションであったわけだが、あれは場に取り憑いた怨念が無関係の人まで巻き込んでいく怖さがあった。「輪廻」の場合、幽霊屋敷と生まれ変わりをミックスさせた結果、関係者のみが犠牲になることになり、それで怖さが半減している(もっとも、誰が関係者であるのかは本人にさえ分からない)。出来事に合理的な説明があるので怖くなくなったし、スケールが小さくなったのは残念だが、映画のまとまりは、脚本がしっかりしているので「呪怨」よりも上だろう。こういうジャンルで新しいアイデアを取り入れるのは容易ではないが、あと一ひねりしたいところだ。
「呪怨」の清水崇監督の新作で、35年前に大量殺人があったホテルを題材にした映画のスタッフとキャストが怪異に襲われるホラー。中心となるアイデアは過去にも例があり、ちょっと考えただけで、設定は異なるけれどもポール・バーホーベンのあの作品とかアラン・パーカーのあの作品が思い浮かぶ。リーインカーネーションを描いた映画としてはこうするか、それこそ「リーインカーネーション」(1976年、J・リー・トンプソン監督)のようにするかしかないのだろう。また、大量殺人のあったホテルと言えば、スティーブン・キング「シャイニング」=映画化はスタンリー・キューブリック=を思い出さずにはいられず、「輪廻」は幽霊屋敷もののバリエーションとも言える(幽霊屋敷の最高傑作は「シャイニング」ではなくリチャード・マシスン「地獄の家」=映画化はジョン・ハフ「ヘル・ハウス」=だと思う)。考えてみれば、「呪怨」自体、幽霊屋敷もののバリエーションであったわけだが、あれは場に取り憑いた怨念が無関係の人まで巻き込んでいく怖さがあった。「輪廻」の場合、幽霊屋敷と生まれ変わりをミックスさせた結果、関係者のみが犠牲になることになり、それで怖さが半減している(もっとも、誰が関係者であるのかは本人にさえ分からない)。出来事に合理的な説明があるので怖くなくなったし、スケールが小さくなったのは残念だが、映画のまとまりは、脚本がしっかりしているので「呪怨」よりも上だろう。こういうジャンルで新しいアイデアを取り入れるのは容易ではないが、あと一ひねりしたいところだ。