2006/03/28(火)「ウォレスとグルミット 野菜畑で大ピンチ!」
 「ハウルの動く城」「ティム・バートンのコープス・ブライド」を抑えてアカデミー長編アニメーション賞を受賞したクレイ(粘土)アニメ。野菜畑を荒らすウサギに対抗する発明家ウォレスと愛犬グルミットの活躍を描く。と、簡単にストーリーは要約できず、途中で狼男や「ザ・フライ」を思わせる展開になる。ウサギ吸引装置の場面などにCGも使っているが、そこもクレイ・アニメの雰囲気に似せて作ったそうだ。イギリスのスタッフらしく、細かいギャグやサスペンスタッチも取り入れて粋な仕上がりである。ただし、あくまでも子供向け。随所にある過去の映画の引用やパロディ的な描写も子供に分かる程度の内容になっている。その品の良さがアカデミーでは好まれたのかもしれない。あまのじゃくなファンとしては、長編よりも5分か10分ぐらいの短編をたくさん見た方が満足感が高いのではないかと思ってしまう。短編の方が向いている題材ではないかと思うのだ。
「ハウルの動く城」「ティム・バートンのコープス・ブライド」を抑えてアカデミー長編アニメーション賞を受賞したクレイ(粘土)アニメ。野菜畑を荒らすウサギに対抗する発明家ウォレスと愛犬グルミットの活躍を描く。と、簡単にストーリーは要約できず、途中で狼男や「ザ・フライ」を思わせる展開になる。ウサギ吸引装置の場面などにCGも使っているが、そこもクレイ・アニメの雰囲気に似せて作ったそうだ。イギリスのスタッフらしく、細かいギャグやサスペンスタッチも取り入れて粋な仕上がりである。ただし、あくまでも子供向け。随所にある過去の映画の引用やパロディ的な描写も子供に分かる程度の内容になっている。その品の良さがアカデミーでは好まれたのかもしれない。あまのじゃくなファンとしては、長編よりも5分か10分ぐらいの短編をたくさん見た方が満足感が高いのではないかと思ってしまう。短編の方が向いている題材ではないかと思うのだ。
巨大野菜コンテストが間近に迫った町で、ウォレスとグルミットは害獣駆除隊「アンチ・ペスト」として畑を守っていた。いたずらウサギを捕まえて、被害を防ぎ、新聞の一面を飾る。それを見たコンテストの主催者レディ・トッティントンから連絡が入り、ウォレスとグルミットはトッティントンの畑にいた大量のウサギを吸引装置で駆除する。捕まえたウサギは地下室で飼っていたが、ウォレスは自分が発明した装置を使って、ウサギを野菜嫌いにしようとする。チーズ好き、野菜嫌いの自分の思考をウサギの脳に送って野菜嫌いにする計画。しかし満月の光も借りて行った実験は失敗に終わる。ある夜、巨大なウサギが畑を荒らす事件が発生。再びかり出されたウォレスとグルミットは先日の実験に使ったハッチと名付けたウサギが巨大化しているのを発見する。ここからのストーリーにはちょっとしたヒネリがある。ヒネリはあるが、ヒネった先は定跡を踏んだ展開で、想像はつく。
いたずらウサギたちの描写は「グレムリン」風で、そこから狼男や「ジキル博士とハイド氏」を思わせる展開になり、最後は「キング・コング」風になる。ウォレスとグルミットに対抗する役柄としてウサギを銃で駆除しようとするハンターのヴィクターとその愛犬フィリップが登場し、生き物を殺さないウォレスとグルミットの人のいいキャラクターを強調しているのが品の良さにつながっている。物語にヒネリはあるが、キャラクターは(少しぐうたらなところはあるけれども)品行方正なのである。そこが映画の心地よさでもあるので、否定はしない。
「ウォレスとグルミット」は時々、カートゥーン・ネットワークで放送している。あれは1分のシリーズなのか、それともアカデミー賞を受賞した短編の方なのか、じっくり見ていないので分からないが、発明家なのにちょっと抜けているウォレスとしっかりしたグルミットの関係はなんとなくチャーリー・ブラウンとスヌーピーの関係を思わせて微笑ましい。日本語吹き替え版はウォレスを萩本欽一、トッティントンを飯島直子が担当。ちょっと違うかなと思ったが、見ているうちに違和感はなくなった。飯島直子には実写映画にも出てほしいものだ。
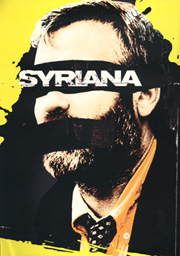 「トラフィック」の脚本家スティーブン・ギャガンが中東とアメリカの石油コネクションをえぐるジャーナリスティックなサスペンス。アメリカの石油資本が中東にどうかかわり、CIAがどんなことをしているかを「トラフィック」同様に多数の登場人物のさまざまな視点から描く。シリアナとはイラン、イラク、シリアからなる、アメリカの利益にかなう新しい国を指す業界用語だそうだ。話が見えない前半は決してうまくいっているとは言えないのだが、後半、話がつながり、全体が見えてくると、面白くなる。少なくとも今に通用する内容なので、「ミュンヘン」や「ジャーヘッド」に感じたジャーナリスティックな側面の欠落という不満はない。問題は題材を面白く見せる技術がギャガンにはまだ不足していることだろう。面白さにおいて同じ手法の「トラフィック」に及ばないのはスティーブン・ソダーバーグとギャガンの演出力の差と言える。
「トラフィック」の脚本家スティーブン・ギャガンが中東とアメリカの石油コネクションをえぐるジャーナリスティックなサスペンス。アメリカの石油資本が中東にどうかかわり、CIAがどんなことをしているかを「トラフィック」同様に多数の登場人物のさまざまな視点から描く。シリアナとはイラン、イラク、シリアからなる、アメリカの利益にかなう新しい国を指す業界用語だそうだ。話が見えない前半は決してうまくいっているとは言えないのだが、後半、話がつながり、全体が見えてくると、面白くなる。少なくとも今に通用する内容なので、「ミュンヘン」や「ジャーヘッド」に感じたジャーナリスティックな側面の欠落という不満はない。問題は題材を面白く見せる技術がギャガンにはまだ不足していることだろう。面白さにおいて同じ手法の「トラフィック」に及ばないのはスティーブン・ソダーバーグとギャガンの演出力の差と言える。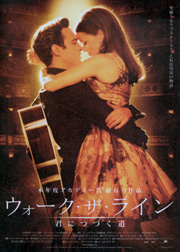 ジョニー・キャッシュ(ホアキン・フェニックス)やジェリー・リー・ルイス(ウェイロン・マロイ・ペリン)やバンドのメンバーが朝から酔っぱらっているのを見てあきれたジューン・カーター(リース・ウィザースプーン)が「まっすぐに歩けない男たちばかりね」と怒る。それでジョニーは「君のために真っ直ぐ歩く」と訴える「アイ・ウォーク・ザ・ライン」という歌を作る。少女時代からステージに立ったジューンの歌をジョニーは少年時代からラジオで聴いていた。手の届かない世界にいると思っていた憧れの女性と同じステージに立ち、一緒にツアーに出るようになって、ジョニーはジューンへの距離を徐々に縮めていく。酒場で初めて心を通わせる場面など2人の関係を描くシーンがとてもいい。ジューンは2度結婚に失敗し、ジョニーも既に結婚していたので、なかなか恋人同士にはなれないのだが、この映画、ジョニー・キャッシュの生涯をジューンとの関係に重点を置いてラブストーリーとして映画化したのが成功の要因だと思う。素敵なラブストーリーになっている。
ジョニー・キャッシュ(ホアキン・フェニックス)やジェリー・リー・ルイス(ウェイロン・マロイ・ペリン)やバンドのメンバーが朝から酔っぱらっているのを見てあきれたジューン・カーター(リース・ウィザースプーン)が「まっすぐに歩けない男たちばかりね」と怒る。それでジョニーは「君のために真っ直ぐ歩く」と訴える「アイ・ウォーク・ザ・ライン」という歌を作る。少女時代からステージに立ったジューンの歌をジョニーは少年時代からラジオで聴いていた。手の届かない世界にいると思っていた憧れの女性と同じステージに立ち、一緒にツアーに出るようになって、ジョニーはジューンへの距離を徐々に縮めていく。酒場で初めて心を通わせる場面など2人の関係を描くシーンがとてもいい。ジューンは2度結婚に失敗し、ジョニーも既に結婚していたので、なかなか恋人同士にはなれないのだが、この映画、ジョニー・キャッシュの生涯をジューンとの関係に重点を置いてラブストーリーとして映画化したのが成功の要因だと思う。素敵なラブストーリーになっている。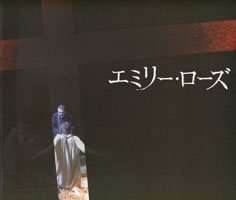 京極堂の力がいるな、と思う。憑物を落とすには京極堂が一番である。日本の狐憑きと同じように西欧の悪魔憑きも精神的な病の一つだろう。昔の人は病名が分からなかったので、狐憑きとか悪魔憑きとか言ったにすぎないのだと思う。この映画は旧西ドイツで1970年代にあった実際の事件をモデルにしている。神父から悪魔祓い(エクソシズム)を受けた女子大生が衰弱死する。その神父が罪に問われ、裁判でまともに悪魔憑きを論じるというのがもう、言うべき言葉をなくす。悪魔がいるとかいないとかの議論は日本人(というか非キリスト教徒)には関係ない世界の話のように思う。精神病の薬をやめさせたことで症状が悪化したという検察側の主張の方にいちいち納得させられるのだが、それでは映画として面白くないと思ったのか、神父の弁護士(ローラ・リニー)の身辺にも奇怪な現象が起きる。これが極めて控えめな怪異なので、ホラーにはなっていない。ホラーなら徹底的にホラー、裁判劇なら裁判劇に徹した方が良かったのではないか。この映画の結論はどっちつかずで面白みに欠けるのだ。映画自体は丁寧な作りだし、弁護士役のローラ・リニーも颯爽としていていいのだけれど、地味な印象は拭えず、平凡な出来に終わっている。題材へのアプローチの仕方が凡庸なのである。
京極堂の力がいるな、と思う。憑物を落とすには京極堂が一番である。日本の狐憑きと同じように西欧の悪魔憑きも精神的な病の一つだろう。昔の人は病名が分からなかったので、狐憑きとか悪魔憑きとか言ったにすぎないのだと思う。この映画は旧西ドイツで1970年代にあった実際の事件をモデルにしている。神父から悪魔祓い(エクソシズム)を受けた女子大生が衰弱死する。その神父が罪に問われ、裁判でまともに悪魔憑きを論じるというのがもう、言うべき言葉をなくす。悪魔がいるとかいないとかの議論は日本人(というか非キリスト教徒)には関係ない世界の話のように思う。精神病の薬をやめさせたことで症状が悪化したという検察側の主張の方にいちいち納得させられるのだが、それでは映画として面白くないと思ったのか、神父の弁護士(ローラ・リニー)の身辺にも奇怪な現象が起きる。これが極めて控えめな怪異なので、ホラーにはなっていない。ホラーなら徹底的にホラー、裁判劇なら裁判劇に徹した方が良かったのではないか。この映画の結論はどっちつかずで面白みに欠けるのだ。映画自体は丁寧な作りだし、弁護士役のローラ・リニーも颯爽としていていいのだけれど、地味な印象は拭えず、平凡な出来に終わっている。題材へのアプローチの仕方が凡庸なのである。