2005/11/08(火)「メゾン・ド・ヒミコ」
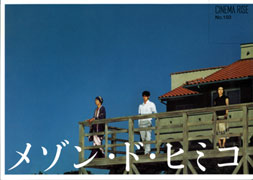 「触りたいとこないんでしょ?」。沙織(柴咲コウ)の言葉が絶望的に響く。ゲイの岸本(オダギリジョー)と沙織の間には越えられない壁があり、心は通い合っても体の関係は結べない。この映画、ゲイと女のラブストーリーという甘ったるい話では全然なく、どこまでも厳しい話である。障害者と大学生の関係を描いた「ジョゼと虎と魚たち」と基本的には同じ構造でありながら、ラブストーリーとしては機能していない。それは父と娘の確執を取り入れたためもあるが、監督の犬童一心には元々、甘い話にするつもりはなかったのだろう。監督の言葉を借りれば、これは「何かを試そうとした」人たちの話であり、その何かとは人と人とを隔てる壁を越えることにほかならない。結局、壁は越えられないのだが、その代わりに映画は小さなハッピーエンドを用意している。これがとても心地よい。柴咲コウ、オダギリジョー、田中泯の好演に加え、テーマを突き詰める姿勢とキャラクターの焦点深度の深さにおいて、今年の邦画の中では群を抜いている映画だと思う。
「触りたいとこないんでしょ?」。沙織(柴咲コウ)の言葉が絶望的に響く。ゲイの岸本(オダギリジョー)と沙織の間には越えられない壁があり、心は通い合っても体の関係は結べない。この映画、ゲイと女のラブストーリーという甘ったるい話では全然なく、どこまでも厳しい話である。障害者と大学生の関係を描いた「ジョゼと虎と魚たち」と基本的には同じ構造でありながら、ラブストーリーとしては機能していない。それは父と娘の確執を取り入れたためもあるが、監督の犬童一心には元々、甘い話にするつもりはなかったのだろう。監督の言葉を借りれば、これは「何かを試そうとした」人たちの話であり、その何かとは人と人とを隔てる壁を越えることにほかならない。結局、壁は越えられないのだが、その代わりに映画は小さなハッピーエンドを用意している。これがとても心地よい。柴咲コウ、オダギリジョー、田中泯の好演に加え、テーマを突き詰める姿勢とキャラクターの焦点深度の深さにおいて、今年の邦画の中では群を抜いている映画だと思う。
渡辺あや脚本で犬童一心監督の「ジョゼ…」コンビの作品ならば、絶対に面白いはずだと思いつつ、見る前に気が重かったのはこれがゲイの老人ホームの話であり、オダギリジョーと田中泯のキスシーンまであると事前に知っていたからだが、映画はそうした観客の偏見を見透かすように主人公・沙織のゲイへの嫌悪感を描いていく。沙織の嫌悪感は父親が40歳の時に母親と自分を捨ててゲイとして生きることを選んだことが影響しており、沙織は父親を未だに許せないでいる。母が死に、借金を背負って小さな塗装会社で働いている沙織は風俗でのバイトも考えるが、そんな時、岸本から週に一度、ゲイの老人ホームである「メゾン・ド・ヒミコ」を手伝ってくれと頼まれる。「メゾン・ド・ヒミコ」は銀座のバーをやめた父親が作った老人ホーム。父親は末期がんにかかっており、死ぬ前に娘に会わせたいと岸本は考えたらしい。1日3万円の報酬目当てで沙織はホームで働くようになる。
ここから映画はホームに住むゲイの老人たちの姿を描き、次第に打ち解けていく沙織と岸本の関係を描く。ホームの面々とともにダンスホールに出かけた2人が「また逢う日まで」に合わせて踊るシーンには素晴らしい高揚感があり、これで2人が一気に親しくなることに納得できる。このシーンの後で沙織は岸本からキスをされ、「なんであたしに…」と戸惑うことになる。
渡辺あやの第1稿が完成したのは2001年1月。犬童一心はそれに注文を付け、間に「ジョゼと虎と魚たち」の撮影を挟んで2004年9月に完成した最終稿は第10稿となった。改稿の過程で沙織の父親とヒミコは同一人物となったそうだ。岸本と体の関係を結べなかった沙織がその反動もあって、会社の専務の細川(西島秀俊)に抱かれてしまう所などにこの脚本の洞察の深さを感じる。細川は女子社員に手を出し続けている俗物で、体だけが目当て。沙織と心だけは通い合った岸本と好対照な存在なのである。それを知った岸本のセリフが切ない。
柴咲コウはノーメイクに近いらしいが、そのために普段でも鋭い目つきがより際立つことになった。父親やゲイへの嫌悪感、多額の借金を背負った必死さに説得力を持たせる鋭い目つきであり、これまでの演技の中ではベストではないかと思う。
2005/11/07(月)「ブラザーズ・グリム」
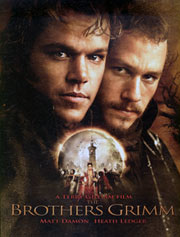 「ラスベガスをやっつけろ!」(1998年)は未見なので、「12モンキーズ」(1995年)以来10年ぶりに見るテリー・ギリアム監督作品。「ほら男爵の冒険」を自由に破天荒に騒々しく映画化し、世間的には失敗作といわれる(しかし僕は傑作と思う)「バロン」(1988年)のような映画かと思ったら、グリム兄弟をモチーフにしたダークなファンタジーだった。至る所にギリアムらしいシニカルさや残酷な味わいは散見されるが、後半がまともな魔物退治になっていくあたりがやや不満で、全体としては平凡な出来と言わざるを得ない。いつものギリアム映画のように、この映画もまた撮影終了から公開まで2年もかかるなど製作過程ではいろいろなゴタゴタがあったそうだ。そういうことが少なからず映画の出来に影響しているのだろう。シーンのつながりでおかしな部分や冗長に思える部分が目についた。
「ラスベガスをやっつけろ!」(1998年)は未見なので、「12モンキーズ」(1995年)以来10年ぶりに見るテリー・ギリアム監督作品。「ほら男爵の冒険」を自由に破天荒に騒々しく映画化し、世間的には失敗作といわれる(しかし僕は傑作と思う)「バロン」(1988年)のような映画かと思ったら、グリム兄弟をモチーフにしたダークなファンタジーだった。至る所にギリアムらしいシニカルさや残酷な味わいは散見されるが、後半がまともな魔物退治になっていくあたりがやや不満で、全体としては平凡な出来と言わざるを得ない。いつものギリアム映画のように、この映画もまた撮影終了から公開まで2年もかかるなど製作過程ではいろいろなゴタゴタがあったそうだ。そういうことが少なからず映画の出来に影響しているのだろう。シーンのつながりでおかしな部分や冗長に思える部分が目についた。
母親と2人の子供が寒さに震えて次男の帰りを待っている。次男は牛を売りに行ったのだ。ところが、次男が持って帰ったのは魔法の豆。詐欺師に騙されてしまったのだった。という「ジャックと豆の木」のような冒頭からジャンプして映画は15年後、19世紀のフランス占領下のドイツで詐欺師として生きるウィルとジェイコブのグリム兄弟の場面となる。兄弟は魔物を退治すると偽って金を稼いでいた。それがフランス軍のドゥラトンブ将軍(ジョナサン・プライス)に発覚し、拷問が趣味の部下カヴァルディ(ピーター・ストーメア)とともに兄弟は子供が次々に失踪している村マルバデンに無理矢理、派遣される。村の事件も兄弟が行ったような詐欺と思われていたが、ここには本物の魔物がいた。子供は既に10人失踪し、11人目も兄弟の目の前で魔物にさらわれる。この村には疫病を逃れて高い塔に閉じこもった女王の伝説があり、子供の失踪はそれに関係しているらしい。森の中には狼男や動く木が潜んでいた。2人の妹をさらわれたアンジェリカとともに兄弟は女王の秘密を探り始める。
「赤ずきん」や「ヘンゼルとグレーテル」などグリム童話を引用しながら物語を作ったアーレン・クルーガー(「スクリーム3」「ザ・リング」)の脚本は可もなく不可もなしといった感じの出来栄え。引用が引用だけに終わって、物語と有効に結びついていず、あっと驚くような展開はない。これだったら、グリム兄弟を主人公に据える意味がない。加えて魔物のVFXも標準的となると、あとはギリアムの演出にかかってくるのだが、これまた標準的なものに終わっている。将軍やカヴァルディのキャラクターは一癖あって面白いのだけれども、ただそれだけのことだった。
現実主義者の兄と空想好きの弟というグリム兄弟を演じるのはマット・デイモンとヒース・レジャーで、2人ともやや地味な印象。悪の女王役のモニカ・ベルッチはもっと出番が多くても良かった。ベルッチの美貌にはとてもかなわないが、兄弟と親しくなる男まさりのアンジェリカ役レナ・へディも悪くない。
ギリアムはこの映画の製作が中断している間に「Tideland」という低予算映画を撮り、公開待機中という。「不思議の国のアリス」をモチーフにしているらしい次作で本当に復活を果たしているかどうか楽しみに待ちたい。
2005/10/31(月)「四月の雪」
 省略が洗練を感じさせ、寡黙さが余韻を生む。描写によって物語を語るのが映画の基本とすれば、ホ・ジノの演出は映像表現の高度な部分を兼ね備えている。セリフで心情を説明するような野暮なことはしていないし、単なる不倫を純愛とも悲恋とも声高に主張したりはせず、ただただ2人の行動を静かに綴るのみだ。これが唯一崩れるのは主演の2人が交通事故死した若者の葬儀に行く場面。ここの類型的な演出は映画のトーンから浮いている。ここは2人が心を通わせる契機となる場面なので、なおさら慎重な演出が必要だっただろう。描写のあまりの自然さは逆に多少の不満にもつながっていて、物語にもう少しひねりを加えてくれないと、日常的な描写ばかりでは一般的な面白みには欠ける。物語をどう表現するかにホ・ジノの関心はあり、物語自体をどう面白くするかに心を砕いてはいないようだ。もちろん、そういう映画の方法もあるので、これは単に好みの問題なのだが、それならば、所々にウェットなピアノ曲など流さない方が良かったと思う。意識的に劇的効果を廃するのならば、音楽は最小限にとどめた方が良かった。
省略が洗練を感じさせ、寡黙さが余韻を生む。描写によって物語を語るのが映画の基本とすれば、ホ・ジノの演出は映像表現の高度な部分を兼ね備えている。セリフで心情を説明するような野暮なことはしていないし、単なる不倫を純愛とも悲恋とも声高に主張したりはせず、ただただ2人の行動を静かに綴るのみだ。これが唯一崩れるのは主演の2人が交通事故死した若者の葬儀に行く場面。ここの類型的な演出は映画のトーンから浮いている。ここは2人が心を通わせる契機となる場面なので、なおさら慎重な演出が必要だっただろう。描写のあまりの自然さは逆に多少の不満にもつながっていて、物語にもう少しひねりを加えてくれないと、日常的な描写ばかりでは一般的な面白みには欠ける。物語をどう表現するかにホ・ジノの関心はあり、物語自体をどう面白くするかに心を砕いてはいないようだ。もちろん、そういう映画の方法もあるので、これは単に好みの問題なのだが、それならば、所々にウェットなピアノ曲など流さない方が良かったと思う。意識的に劇的効果を廃するのならば、音楽は最小限にとどめた方が良かった。
最も残念なのは、これは監督の責任ではないけれど、韓流ブームの中核的な映画としてパッケージングされていることだ。主演がペ・ヨンジュンである必要はなかったし、そうでない方が下手な反発にはさらされず、映画の本質は見極めやすくなっただろう。
キネ旬10月上旬号のインタビューでホ・ジノはヨンジュンについて、こう語っている。
「後半になって、インスが能動的に動くのが難しい状況に追い込まれてからは、私はもう少し間接的で深みのある演技をしてほしかったけれど、俳優としては何か積極的に動ける表現がしたかったようです。これは私の映画に出演する俳優たちが共通して持つ希望ですけれど……」
感情表現を俳優にはできる限り抑えさせ、それを別の描写によって表現するというホ・ジノの方法がヨンジュンには理解できなかったらしい。ヨンジュンが溌剌とするのは不倫の一線を踏み越えた後に見せる笑顔であり、この脳天気な笑顔がヨンジュンという俳優のキャラクター的限界を表しているように思う(「スキャンダル」の時のようにメガネを外せば何とかなったか)。監督の意図を理解できなかったのは“韓国の宝石”と称されるソン・イェジンにも言えることかもしれない。得意の泣く演技を封じられたイェジンはそれによって、別の魅力を引き出されることになった。ヨンジュンと会う前にシャワーを浴びる女心やベッドシーンのエロティシズム。清純さとは異なるそうした大人の女の魅力をイェジンは見せており、クロースアップを多用した撮影がそれを余すところなく伝えている。
ホ・ジノはこの映画を長く撮ってたくさん切ったという。無駄な部分を切りつめていく作業こそが洗練を生む。それをよく理解しているのだと思う。饒舌を廃した寡黙な映画。かつてはそういう映画が邦画にもあったが、今はほとんど見かけることがなくなった。しかし、この何ということもないストーリーの映画を支えているのはそうした方法論なのである。ほとんど純文学のノリに近いこの方法では大衆性を得ることは難しいと思う。だからといって、ホ・ジノの価値が損なわれることがないのもまた確かなことではある。
2005/10/30(日)「ティム・バートンのコープス ブライド」
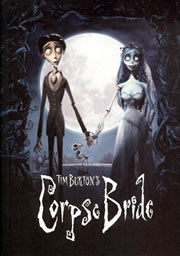 ティム・バートン監督のストップモーション・アニメーション。子供を連れて日本語吹き替え版で見た。だからオリジナルの歌の良さやジョニー・デップ、クリストファー・リー、ヘレナ・ボナム=カーターなどのセリフ回しなどは楽しめなかったのだが、それでもそれなりに面白い(欲を言えば、吹き替え版であっても歌だけは原曲を使ってほしいと思うが、子供のことを考えれば無理なのかもしれない)。個人的には「チャーリーとチョコレート工場」よりもこちらの方が好きである。物語を過不足なく(ストップモーション・アニメとしては大作の1時間17分に)まとめた作りは見事。ダークな雰囲気の中でクスクス笑わせながら温かいストーリーを語るのはバートンらしく、それを忠実にアニメ化したのが共同監督のマイク・ジョンソンなのだろう。完璧なアニメーティングと構図に加えて、セットの造型も細かく丁寧である。良い出来だと思いつつ、何だか物足りない思いも残るのはこれがチョコレート工場同様にファミリー向け映画だから。もちろんだからこそ、子供を連れて行ったのだれども、「スリーピー・ホロウ」「バットマン リターンズ」のようなバートン映画が好きなファンとしてはファミリー映画ばかり作らず、次作こそは大人向けの映画を作ってほしいと切に願う。
ティム・バートン監督のストップモーション・アニメーション。子供を連れて日本語吹き替え版で見た。だからオリジナルの歌の良さやジョニー・デップ、クリストファー・リー、ヘレナ・ボナム=カーターなどのセリフ回しなどは楽しめなかったのだが、それでもそれなりに面白い(欲を言えば、吹き替え版であっても歌だけは原曲を使ってほしいと思うが、子供のことを考えれば無理なのかもしれない)。個人的には「チャーリーとチョコレート工場」よりもこちらの方が好きである。物語を過不足なく(ストップモーション・アニメとしては大作の1時間17分に)まとめた作りは見事。ダークな雰囲気の中でクスクス笑わせながら温かいストーリーを語るのはバートンらしく、それを忠実にアニメ化したのが共同監督のマイク・ジョンソンなのだろう。完璧なアニメーティングと構図に加えて、セットの造型も細かく丁寧である。良い出来だと思いつつ、何だか物足りない思いも残るのはこれがチョコレート工場同様にファミリー向け映画だから。もちろんだからこそ、子供を連れて行ったのだれども、「スリーピー・ホロウ」「バットマン リターンズ」のようなバートン映画が好きなファンとしてはファミリー映画ばかり作らず、次作こそは大人向けの映画を作ってほしいと切に願う。
結婚を翌日に控えた青年ビクターが森の中で誓いの言葉の練習をしたために死体の花嫁(コープス・ブライド)エミリーと結婚する羽目になる。親が決めた婚約者ビクトリアを一目で好きになっていたビクターはさてどうする、というシチュエーション。ビクターの両親は成金で、ビクトリアの家は金庫がスッカラカンの貧乏貴族。富と名声をそれぞれに欲した両親が進めた結婚話だったが、ビクターのナイーブさとビクトリアの清楚さはそれぞれが惹かれ合うのに十分な理由を持っている。一方、エミリーは幸福な結婚を夢見ていたのに結婚してすぐに夫から殺されてしまった過去がある。この3人の善良な三角関係に絡んでくるのが正体不明の男バーキスで、この映画唯一の悪役である。生者か死者か、ビクターはどちらを選ぶのか。普通なら生者を選ぶに決まっているが、映画は死者の世界を明るいカラーで、生者の世界はモノクロームに近いくすんだ色合いで描き、死者の世界のデメリットを打ち消している。バーキスの存在は三角関係の解消による切なさを和らげる方向に働いており、この脚本、なかなか巧妙だ。つまり、結ばれた2人だけでなく、取り残された1人にも満足感が得られる構造になっているわけである。
ストップモーション・アニメの常で技術的な部分についつい目が行ってしまう。「キング・コング」(1933年)の昔からストップモーション・アニメはどこか動きにぎこちない部分が残るものだが、この映画、一瞬、CGではないかと思えるほど滑らかな動き。花嫁のブーケやドレスが風に揺れるシーンなど極めて自然である。この撮影、なんとデジタル・スチール・カメラが使われたという。スチール・カメラの画像を1秒間に24コマつなげれば、確かにアニメになるのだが、その作業は想像を絶するほど根気のいるものだろう。いや、ストップモーション・アニメは元々根気のいるものであり、画像の処理がデジタルならば簡単にできるという利点は確かにあるのだが、スチールを使うというのは普通は考えない。これはもう気分的なもので、ムービーカメラを使ったにしても一コマずつ撮っていくしかないのだから、スチールで撮ったって別に構わないのだ。編集もパソコンでできるメリットがある。そうした技術的な部分を映画からは感じさせないのが良いところで、技術が物語を語る手段に収まって前面に出てこないのは好ましい。
2005/10/26(水)「ドミノ」
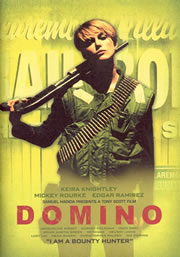 実在した女賞金稼ぎドミノ・ハーヴェイを描くアクション映画。というよりはアクション映画のストーリーに実在の賞金稼ぎをはめ込んだと言うべきだろう。中心となる事件がうまくできすぎていて、いかにもフィクションという感じがある。マフィアと現金輸送車強奪グループと賞金稼ぎの三つどもえの争いとなるこの事件自体は、誤解と陰謀が絡み合って面白い。監督のトニー・スコットはミュージック・ビデオのような映像で物語を綴っていく。短いカット割りとフラッシュバック、ざらついた映像の連続は、しかし、効果を上げているとは言えない。スタイリッシュを目指したと思えるのにそうなっていず、感情移入を拒否して見にくいだけなのである。同じく凝った映像で楽しませた「シン・シティ」と比べれば、両者の優劣は歴然とするだろう。それ以上に問題なのは端的に「ドミノ」にはハートがないこと。ドミノのキャラクターや仲間との関係が極めて表層的なものに終わっており、エモーションが高まっていかない。主演のキーラ・ナイトレイは悪くないだけに残念だ。
実在した女賞金稼ぎドミノ・ハーヴェイを描くアクション映画。というよりはアクション映画のストーリーに実在の賞金稼ぎをはめ込んだと言うべきだろう。中心となる事件がうまくできすぎていて、いかにもフィクションという感じがある。マフィアと現金輸送車強奪グループと賞金稼ぎの三つどもえの争いとなるこの事件自体は、誤解と陰謀が絡み合って面白い。監督のトニー・スコットはミュージック・ビデオのような映像で物語を綴っていく。短いカット割りとフラッシュバック、ざらついた映像の連続は、しかし、効果を上げているとは言えない。スタイリッシュを目指したと思えるのにそうなっていず、感情移入を拒否して見にくいだけなのである。同じく凝った映像で楽しませた「シン・シティ」と比べれば、両者の優劣は歴然とするだろう。それ以上に問題なのは端的に「ドミノ」にはハートがないこと。ドミノのキャラクターや仲間との関係が極めて表層的なものに終わっており、エモーションが高まっていかない。主演のキーラ・ナイトレイは悪くないだけに残念だ。
映画は警察の取調室でFBI捜査官(ルーシー・リュー)の聴取に答えて、ドミノが事件を回想する形式。ドミノは俳優ローレンス・ハーヴェイとモデルの母親(ジャクリーン・ビセット)の間に生まれた。高校時代からスーパーモデルとして活躍したが、セレブな生活に嫌気が差して、新聞広告で募集記事を見つけた賞金稼ぎ(バウンティ・ハンター)となる。映画の前半は実際のドミノの奔放な人生を描いていく。メインの事件が始まってからはほとんどフィクション(映画の冒頭にはBased on a True Storyと出た後にSort of ...とただし書きがつく)。賞金稼ぎのボスはエド(ミッキー・ローク)、仲間はチョコ(エドガー・ラミレス)とアフガニスタン人の運転手アルフ(リズワン・アビシ)。これに保釈金保証人クレアモント(デルロイ・リンドー)、ドミノを取材するテレビ局スタッフ(クリストファー・ウォーケンが変人プロデューサー、「アメリカン・ビューティー」のミーナ・スヴァリが美人スタッフを演じる)、マフィア、カジノのオーナー、現金輸送車強奪グループが絡まり合ってストーリーが進む。
脚本は「ドニー・ダーコ」のリチャード・ケリー。メインの事件の描き方は、映画の最初の方から事件の断片を入れていくところなどガイ・リッチー「スナッチ」を思わせる。これは人命がかかった事件なので、もっとエモーショナルなものになっていくはずなのだが、この映画の描き方ではそれが希薄になってしまう。希薄なのはドミノとチョコの関係にも言え、クライマックス前のラブシーンが盛り上がらないのはそれまでの2人の関係の描き方が不十分だからだろう。凝った映像だけがあって、中身がない映画になってしまっている。描写を積み重ねて登場人物の内面まで描き出していくような演出に欠けているのである。MTV出身の監督にはこういうケースがよくあるが、ベテランと言えるトニー・スコットがこういう映画を撮っているようでは困る。
映画の最後に登場する実際のドミノ・ハーヴェイはフランセス・マクドーマンドのような容貌だった。ドミノは今年6月27日、自宅の浴槽で死んだ。35歳。死因は特定されていないが、麻薬の大量摂取が原因とされているという。母親役のジャクリーン・ビセットは久しぶりに見た。かつてはキーラ・ナイトレイ同様、指折りの美人女優だったが、細かいしわが顔全体に刻まれていて、あまりと言えばあまりの老けよう。61歳だから仕方がないのだが、それにしてもこんなに老けるとは驚きである。