2006/01/03(火)「ZOO」
乙一の短編集の中から5編を5人の監督(金田龍、安達正軌、水崎淳平、小宮雅哲、安藤尋)がオムニバスで映画化。「カザリとヨーコ」「SEVEN ROOMS」「SO-far ソ・ファー」「陽だまりの詩」(アニメ)まで見て、なかなかバラエティに富んでいて面白いと思ったが、最後の「ZOO」がよく分からない。積ん読状態(「カザリとヨーコ」のみ読んでいた)だった原作を読んだら、ああこういう話かと納得できた。映画の方はフェリーニ「悪魔の首飾り」のような雰囲気だが、話が分かりにくいのでは仕方がない。
「SEVEN ROOMS」には須賀健太(「三丁目の夕日」)、「SO-far ソ・ファー」には神木隆之介(「妖怪大戦争」)が出ていて、どちらもうまい。「陽だまりの詩」はロボットが出てくる破滅SFで、こういう話は好きである。
2005/12/28(水)「ホステージ」
ロバート・クレイスの原作を「スズメバチ」のフローラン=エミリオ・シリが監督したアクション。これは見逃した後に原作が「ミステリ・マガジン」で評価されていたので、気になっていた。セキュリティ設備が完備した邸宅に3人の若者が人質を取って立てこもる。その家の主人は犯罪組織の会計士。組織は事件解決の指揮をする警察署長の妻と娘を人質に取り、情報が入ったDVDを渡すよう脅迫する。二重の人質事件という発想が良く、ブルース・ウィリス主演の映画としては久しぶりに面白い(もちろん、この後の「シン・シティ」も面白かった)。格好いいタイトルから始まってサスペンスが持続する作りはなかなかのもの。犯罪組織があっけなくやられるあたりはまあ、上映時間の関係上、仕方ないのかもしれない。
DVDに収録されたスタッフ紹介によれば、監督のシリは「ジャン=ピエール・メルヴィルに心酔する一方、ジョン・フォード、ハワード・ホークス、サム・ペキンパー、ジョン・カーペンターの影響を受けている」とある。正統派のアクション映画監督なのだろう。
2005/12/26(月)「チキン・リトル」
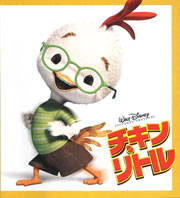 ディズニーとしては初めての全編3DCGのアニメ。上映時間は1時間21分と短く、明らかに子供向けの作りである。アメリカでヒットしたのは子供を連れた親が映画館に詰めかけたからだろう。アメリカでも子供向け作品がヒットするのは日本と同じ理由があるのである。内容的にはディズニーが配給しているピクサーの3DCGアニメに比べると、物足りない部分が多く、ストーリー的にも技術的にもあまり見るべきところはない。昨年公開されたピクサーの「Mr.インクレディブル」と比べれば、その差はとても大きいと思う。それでも小学生の子供は喜んで見ていたから、ディズニーの狙いは間違ってはいないのだろう。監督は「ラマになった王様」のマーク・ディンダル。演出に大きな不備はないが、特に優れた部分も見あたらない。つまり平凡である。ディズニーが今後も3DCGアニメを作るつもりなら、脚本にもっと力を入れて、子供と一緒に見る親も楽しめる映画を目指した方がいいと思う。
ディズニーとしては初めての全編3DCGのアニメ。上映時間は1時間21分と短く、明らかに子供向けの作りである。アメリカでヒットしたのは子供を連れた親が映画館に詰めかけたからだろう。アメリカでも子供向け作品がヒットするのは日本と同じ理由があるのである。内容的にはディズニーが配給しているピクサーの3DCGアニメに比べると、物足りない部分が多く、ストーリー的にも技術的にもあまり見るべきところはない。昨年公開されたピクサーの「Mr.インクレディブル」と比べれば、その差はとても大きいと思う。それでも小学生の子供は喜んで見ていたから、ディズニーの狙いは間違ってはいないのだろう。監督は「ラマになった王様」のマーク・ディンダル。演出に大きな不備はないが、特に優れた部分も見あたらない。つまり平凡である。ディズニーが今後も3DCGアニメを作るつもりなら、脚本にもっと力を入れて、子供と一緒に見る親も楽しめる映画を目指した方がいいと思う。
「狼少年」に「宇宙戦争」を加えて父と息子の相互理解をテーマにした話である。1年前、チキン・リトルは「空のかけらが落ちてきた」と警報の鐘を鳴らす。町中は大騒ぎになるが、確かに見たはずの六角形の空のかけらは消えていた。父親も信じてくれず、結局、ドングリと間違ったのだろうということになってしまう。それ以来、チキン・リトルは何をやっても失敗ばかり。体育の授業中、いじめられたアヒルのアビーをかばおうとしたチキン・リトルは火災報知器のスイッチを引いてしまい、スプリンクラーが動作して体育館は水浸し。父親はますますチキン・リトルの話を聞いてくれなくなる。チキン・リトルは野球選手として有名だった父親を見習って野球で名誉挽回を図ろうとする。
ちょっとした計算違いではないかと思うのはベンチ・ウォーマーだったチキン・リトルが代打で出場してヒットを打ってしまうこと。これで少なくとも父親はチキン・リトルを見直すので、ここで終わってもいいなと思えるのである。これに続く空のかけらの真相が分かるシーンは明らかに「宇宙戦争」で、宇宙船からトライポッドのような機械が出てきたり、人を消滅させる光線を出すあたり、スピルバーグのリメイク作品とよく似ている。公開時期から考えて模倣ではないが、結果的に目新しさには欠けることになった。このシーンによって、チキン・リトルは町の住民たちからも見直されることになる。ただし、この展開、物語を派手にするための展開のような気がしないでもない。話自体にあまりオリジナリティーが感じられず、志は高くないと思う。ついでに言えば、ギャグのレベルも高くはない。
みにくいアヒルの女の子アビーについては明らかに差別的な表現があり、少し気になった。チキン・リトルはアビーに好意を寄せるのだが、アビーの外見を超えた内面の魅力が描かれないので終盤のキスシーンが唐突に思える。チキン・リトル自体はかわいいキャラクターなのに、他のキャラクターはあまりかわいらしさのないデザインが多かった。
2005/12/23(金)「HINOKIO」
引きこもりの少年が遠隔操作のロボット(ヒノキが一部に使われているのでヒノキオとあだ名が付く)で学校に行くようになり、友人との交流を通じて引きこもり生活から脱する。よくできたジュブナイルだと思うが、題材を詰め込みすぎて未消化に終わった部分が多い。現実とリンクしているゲーム世界の扱いなど中途半端。ゲームが現実を浸食してくるような展開になると好みの映画になったと思う。驚くのはCGで作られたヒノキオの自然さで、どれがCGでどれが本物か見分けがつかない。この技術はハリウッドに負けていない。
監督の秋山貴彦はVFXマン出身。山崎貴のデビュー作「ジュブナイル」もドラマ的には弱い部分が多かったから、秋山貴彦にも2作目を期待したい。
主人公を演じるのは「大停電の夜に」の本郷奏多。友人役の田部未華子は最初、少年かと思っていたら、少女と分かる場面でびっくり。要注目。堀北真希が小学生役で出ていて、これもびっくり。キャスト紹介を見るまで堀北真希とは分からなかった。堀北真希はいろんな役柄ができるのに感心する。今年は映画に3本出たのかな。
2005/12/20(火)「男たちの大和」
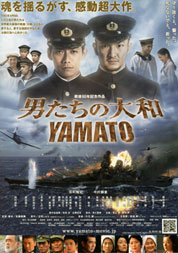 エンドクレジットにがらがら声の聞くに堪えない歌が流れる。なぜ金払ってこんなヘタクソな歌を聴かされなければならないのかと腹が立ってくる。誰だ、この下手な歌手はと思ったら、長渕剛だった。かつて「二百三高地」でさだまさしの歌が流れた時は映画の良さをぶち壊しにしやがってと思ったものだが、この映画の場合は映画本編自体が優れているわけではない。監督は佐藤純弥。だから期待はあまりしていなかった。ただ、佐藤純弥には「新幹線大爆破」という唯一の大傑作がある。脚本が良ければ、化ける可能性はある。しかし、劇場に入ってパンフレットを見たら、脚本も佐藤純弥が手がけていた。この時点で期待は消滅した。2時間23分の映画の中で、どれか一つでも良いシーンがあればいいだろうという消極的な見方になった。
エンドクレジットにがらがら声の聞くに堪えない歌が流れる。なぜ金払ってこんなヘタクソな歌を聴かされなければならないのかと腹が立ってくる。誰だ、この下手な歌手はと思ったら、長渕剛だった。かつて「二百三高地」でさだまさしの歌が流れた時は映画の良さをぶち壊しにしやがってと思ったものだが、この映画の場合は映画本編自体が優れているわけではない。監督は佐藤純弥。だから期待はあまりしていなかった。ただ、佐藤純弥には「新幹線大爆破」という唯一の大傑作がある。脚本が良ければ、化ける可能性はある。しかし、劇場に入ってパンフレットを見たら、脚本も佐藤純弥が手がけていた。この時点で期待は消滅した。2時間23分の映画の中で、どれか一つでも良いシーンがあればいいだろうという消極的な見方になった。
辺見じゅんの同名ノンフィクションの映画化で、大和の乗組員に焦点を絞った話である。語り手役は海軍特別年少兵として大和に乗艦した神尾克己。神尾は生き残り、現在は鹿児島県枕崎市で漁師になっている。そこへ同じく大和乗組員だった内田守の娘がやってくる。娘は父親の遺骨を大和が沈んだ海に散骨したかったのだ。神尾は自分の小さな船で大和の沈んだ海域まで娘を連れて行くことになる。そして大和の運命と乗組員たちを回想する。
一般の兵士に焦点を当てた戦争映画と言えば、「二百三高地」「大日本帝国」の笠原和夫脚本とついつい比較したくなる。「三反百姓には現金収入がないんです」。神尾の友人の西が「なぜ志願したのか」という神尾の母親に対してそう答える場面があるが、笠原和夫ならば、これを膨らませて観客の紅涙を絞っただろう。実際、「二百三高地」には東北の貧しい農村出身の男の話があった。戦争に行かされるのはいつも貧しい層なのだ。上が始めた戦争で庶民がばたばたと犠牲になる。そうした庶民の思いを描き尽くしていただろう、笠原和夫ならば。「さようならあ、おかあさーん」。出撃を前にした年少兵たちが本当にそう言ったのかどうかは知らないが、描き方としてもう少しリアルなものが欲しい。これに限らず、この映画のセリフは下手である。真に迫っていない。だから設定は悪くないのに心を動かされない。比較のために「二百三高地」のセリフを引用しておく。
自分は悔いることは毛頭ありません…
最前線の兵には、体面も規約もありません。
あるものは、生きるか死ぬか、それだけです…
兵たちは…死んでゆく兵たちには、
国家も軍司令官も命令も軍規も、そんなものは一切無縁です。
焦熱地獄の底で鬼となって焼かれてゆく苦痛があるだけです…
その苦痛を…部下たちの苦痛を…
乃木式の軍人精神で救えますか!
佐藤純弥は誰かに脚本の応援を頼む気持ちはなかったのか。右も左もない、庶民の思いをすくい上げることのできる脚本家がこの映画には必要だったのだと思う。
映画は大和の実寸大セットを6億円かけて造ったそうだ。これがいかにも作り物という感じなのは興ざめだが、それ以上に戦闘シーンの工夫のない撮り方の方が問題だろう。大和の全体構造さえ分からず、爆撃を受けて死んでいく兵士を単調に積み重ねるのみ。撮影監督の阪本善尚は「パール・ハーバー」のようにならないようにと注意したそうだが、「パール・ハーバー」の方がましだった。全体としてひどい出来ではないのだが、凡庸を絵に描いたような映画。描きたい思いはあるのに技術が伴わなかったということか。もっとしっかり作ってほしかった。
俳優の序列では中村獅童と反町隆史がトップに来るが、映画の構成では神尾役の松山ケンイチが中心になってしまう(現在の神尾を演じるのは仲代達矢)。これも計算違いだろう。東映配給の大作らしく渡哲也や林隆三、奥田瑛二、長嶋一茂、本田博太郎、勝野洋などがチラリと顔を見せる。チラリとしか出てこない俳優では寺島しのぶが良く、中村獅童との絡みの部分でドラマの雰囲気が立ち上る。